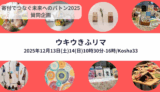こんにちは!ライフデザインラボ所長の船本由佳です。
月に一回のメールマガジン『ライフデザインラボ通信』でラボの活動情報をお届けします。
今年は戦後80年です。この夏、平和について考える機会が増えました。
戦争は起きてほしくないです。そのために個人でできることは何があるでしょうか。
世界の国々の紛争のニュースが聞こえてきます。
日本国内でも多様性を唱える一方で小さな分断がいくつも起きているように感じます。
インターネットの中では、意見の違う他者を攻撃する場面が見られます。
この夏は選挙があり、意見の違う人の存在を感じる機会が多くありました。
戦争が、「対話(平和的解決方法)がない状態」「わかり合えない状態」だとすると、その反対は「対話がある状態」「わかり合おうとする状態」です。
「対話がある状態」に欠かせないのが「メディアリテラシー」。
情報を受け取り、発信する力「メディアリテラシー」を身につけることは、各自でできる平和へのアクションです。
ただ、意見の違う人と話すのは正直に言うとしんどいことです。特に日本人は「相手も自分と同じだろう」「言わなくてもわかるだろう」という考える人が多いので意見の違う他者と話す意識が低いと言われています。
インターネットの中では「フィルタリングバブル」が起きていて、自分に近い人の意見ばかりが目に入るようになるため、自分が多数派であると考えるようになってしまいます。
また、短い動画でものごとを判断する習慣を持つ人も増えていて、本来は複雑だったり経緯を知らなくては理解できないことを読み解ききれずに、誤解をしたりミスリードすることも増えています。
対話の末にわかり合えないと自分も傷つくし、衝突することになったらつらいですよね。私もできれば避けたいなと思ってしまいます。
しかし、多様性社会において、他者と自分が違うことは当たり前なので避けられません。面倒くさいからといってわからないまま過ごすよりも、「わかり合おうとする意識」「わかりあうためのコツ」を持つことは、日常生活の中でできる小さな平和へのアクションです。
迎合でも論破でもない、共感で終わらない対話の仕方を、平和な今の日常の中で身につけていきたいです。
また、どんなに意見が違うもの同士でも同じ空間にいられるという観点で、文化芸術やスポーツの平和的意味は深いのだと思います。
世界平和というと自分個人の行動ではどうにもならないと思ってしまいますが、自分と他者は違うという前提のもと、将来「戦争」を選択しないために、平和的な解決方法の成功体験を積み重ねていきたいと感じました。
子どもには特に対話や交渉などの経験を普段から重ねさせてあげたいです。
なんだか、理屈っぽくなってしまいましたが、さまざまな戦争がなぜはじまったのかを考えていて自分ができることを徒然と考えたことを書き記してみました。
もしみなさんが感じたこと、考えたことがあったらぜひ知らせてください。
このメールに返信すると私たちに届きます。
ラボのメルマガは毎月第3金曜日にお送りしています。
月に一回のライフデザインラボの活動報告、ぜひ読んでください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市民ライターまゆみの取材ノート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月23日(土)に、関内にあるbenten103で「ぷれゆめマルシェ」が開催されます。
ぷれゆめマルシェは、小学生が店主となって自分たちの手で商品やサービスを提供するお仕事を体験できるイベントです。子どもたちは、事前にマネーセミナーを受講して、マルシェ当日に向けてお店のコンセプトを考えたり看板をつくったり、夏休み期間をつかって準備をしています。
ぷれゆめマルシェを主催するのは、ライフデザインラボ研究員でもあり、消しゴムはんこ屋さんの富澤佳代さんです。かよさんは、大学生の息子をもつ母でもあり、benten103のコミュニティスタッフをしたり、NPO法人湘南ビジョン研究所に所属し海の環境問題解決に取り組んだり、いろいろな地域活動にも参加しています。
わたしは、7月10日発行の『横浜の子育て応援マガジン ベイ★キッズvol.57』で、かよさんのぷれゆめマルシェ開催への思いやご自身の子育て経験についてインタビューしました。ベイ★キッズは各区の子育て支援施設や幼稚園・保育園等で配布されています。ベイ★キッズマガジンのウェブサイトでウェブ版もダウンロードできますのでぜひご覧ください。
かよさんが「子どもたちの自主性やチャレンジ精神を応援したい」という気持ちで始めたぷれゆめマルシェ。当日は、わたしも、4歳と6歳の子どもたちを連れて遊びに行きたいと思います。少し先の先輩たちが熱心に取り組む姿は子どもたちの目にも輝いて見えるのではないでしょうか。わたしも、どんなお店が並ぶのか、今から楽しみです!
担当はほんだまゆみでした。